|
ギムノカリキウム・天平丸・レシィ このレシィと言う天平丸。 数年前から、種子業者でチラホラ表れるようになっています。 しかしながら、殆ど情報が見当たりません。 オロモウツ/Olomouc(チェコの都市)のサボテンクラブのWEBページにわずかに心当たりがあるくらいです。 今回、①ChatGPTでチェコ語の文章を英語化 → ➁テーマごとに箇条書きへ変更 → ③専門用語の訳語を食わせて日本語化処理してみました。 以下ChatGPTが吐き出した内容です(一部、ひどく分かり難い所は加筆・修正しています) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ギムノカリキウム・天平丸・レシィ(Gymnocalycium spegazzinii v.recii) 分類: サボテン科 出典: Cactaceae etc. 2017/1, pp. 33 – 36。 根の形状: 主根はわずかに蕪(カブ)形で非常に長く、少数の側根があり、主根の末端部から豊富に形成される。 全体的な形状:平らな球形であり、直径7 - 10 (20) cm、高さ3 - 8 cmである。 部分的には土壌に沈み込んでいる。頂部は深く刺と毛で覆われている。 表皮: 若い植物では暗緑黒色であり、後には青銅色から黒緑色に変化する。 稜: 10 - 13 (-18)本あり、頂部は約1 cm幅、下部は約1.5 - 2 cm幅である。 切れ込みがわずかに波打ち、基部の稜では切れ込みが殆ど確認できない。 アレオーレ: 小円形で、3 mm幅で5 - 7 mm長く、わずかに凹んでいる。 最初は豊富な灰色がかった黄白色の毛で覆われ、後に黄灰色、白灰色になり、最終的には裸になる。 刺: 5 - 7本あり、放射状で針状である。 花: 果皮は紫青色で、わずかにしわが寄っている。果実は梅青色である。 原産地: アルゼンチン、Tucuman州、Quilmesの近辺、特に「Ruinas de Quilmes」産が最も良く知られる。 ホロタイプ(*1): オロモウツ地域博物館の標本室にB171479という番号で保存されている。 特徴: 他の種と異なり、果皮の色、表皮の色、および刺の漆黒色がタイプ種 (*2)と異なる。 命名: オロモウツ市サボテンクラブの会長であり、スポンサーでもあるミハル・レック(Michal Rec)氏にちなんで名づけられた。 (*1)ホロタイプ(Holotype)は、新種の学名記載をする時に1点だけ選ばれる標本。 この1点以外の標本は、参考用としてパラタイプなどと呼ばれる。 (※ここの部分は無茶苦茶複雑です。ざっくりとした説明です) (*2)”タイプ種”(模式種)とはGymnocalcycium spegazzinii (天平丸)の基本となった種 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 【感想】 全般的に、根、表皮、稜、アレオーレなど細かな情報満載。 夢野久作のドグラマグラにある「チャカポコ・チャカポコ」並みに読むのが苦痛です。 ただ、標本の保管場所や、命名の背景に関して、オロモウツ市(10万人都市)の地方色豊かなのに驚きました。 ・・・というか、10万人都市で、ホロタイプを保管する博物があるなんて凄いな~。 どちらかと言うとオロモウツ市の方に興味湧きました。 毛で覆われている事を繰り返し指摘していますが、確かに、本種は何となく普通の天平よりも若干モコモコ感があるかもしれません。 ロフォフォラ名人の育て方だと面白い姿になってくれるかもしれません。 私は出来そうにありませんが・・・ 【出典】 https://www.carciton.cz/kaktusy/clanky9.htm 【追記】 ちなみに、上の説明、やはり本当に分かり難い。 ただ単に、私の植物に対する知的基礎体力の無さなのかもしれませんが・・・ こんな時は、大阪のおっちゃんに分かりやすく解説してもらおうと、 ChatGPTに天下茶屋に住んでいるサボテン好きなおっちゃん(HN: サボ源之助さん(68歳:サボテンクラブでは若手)になってもらい説明してもらいました。 - - - - - - - - - - - - - - - 以下、天下茶屋のサボ源之助さんの解説- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - おおよそこんな感じやな、この文章。 まず根っこやで。メインの根っこはちょっとカブみたいな形で、長いねん。 そこからあんまり枝根は出てこないけど、奥の方に行くとたくさん出てくるんや。 それはなんとなく深いところから出てくる。 で、本体やろ?丸っこいんやけど、ちょっと扁平な感じで、直径が7~10センチくらいやねん。 高さは3~8センチくらいで、土に半分くらい埋まってるねん。 てっぺんは深くてトゲと毛で覆われとる。 最初は濃い緑やけど、後で青銅色みたいになるんや。 で、稜ってのは植物の体の段々のことやで。 このサボテンは10~13本(18本もあることもあるらしい)の稜があって、上の方は1センチくらいの幅やけど、下の方に行くともっと広くなるねん。 稜の上の部分は3~5ミリの高さがあって、下の方ではフラットになるわ。 稜同士はちょっと起伏があるけど、下の方ではほとんどわからんくらいや。 アレオーレってのはトゲが生える部分やねん。 これがちょっと埋まってて、最初は毛で覆われとる。 後で黄色っぽくなって、その後白っぽくなるんや。 アレオーレ同士は1.5~2.5センチくらい離れてるねん。 トゲは5~7本生えとるで。周りに生えるトゲは針みたいな形で、横に2~3対、下に1本や。 横のトゲは上向きに曲がっとることが多いねん。 ちなみに新しいトゲは黒褐色で、次第に黒っぽい角色になってくるねん。 お年寄りのサボテンのトゲは同じ本数やけど、ちょっと爪みたいな形になってて、根本に曲がってるねん。 お花や果皮の色は紫から青色やで。 原産地はアルゼンチンのトゥクマン州のキルメスの近くや。 オロモウツの地域博物館の植物標本室にホロタイプが保管されとるねん。 この種は他の天平丸(spegazzinii)のサボテンと違って、果皮の色や本体の色、トゲの真っ黒い色が特徴やねん。 名前の由来はオロモウツの組織の会長で、オロモウツのサボテン育成のスポンサーやったミハル・レック氏から来てるねん。 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - むっちゃ分かりやすい! やるなサボ源之助68歳。南海の特急の指定席がホームから遠い! と文句言ってるだけちゃうやん! むっちゃ分かりやすい。
0 コメント
あなたのコメントは承認後に投稿されます。
返信を残す |
カテゴリ
すべて
アーカイブ
7月 2024
運営者近畿の住宅地の中でサボテンや多肉を育てています。 |

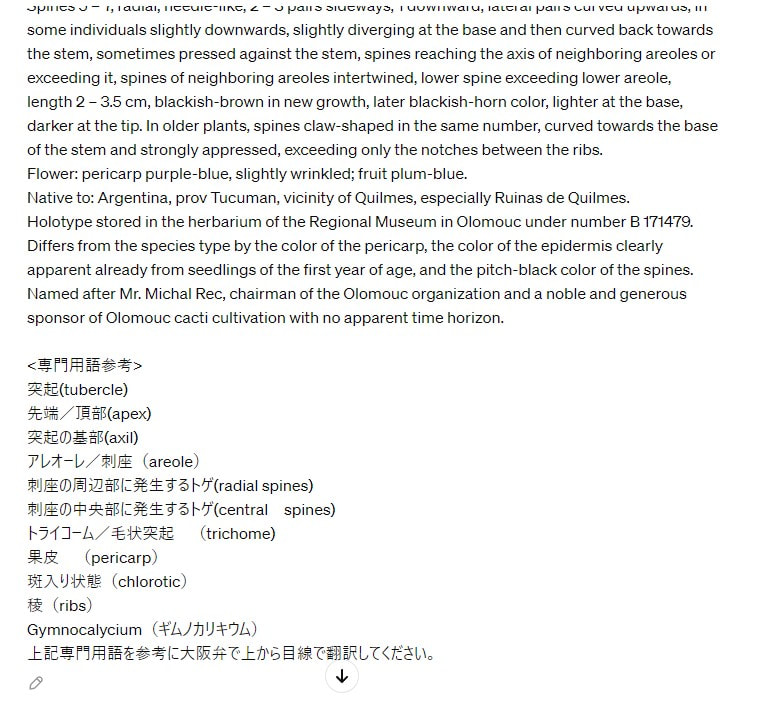
 RSSフィード
RSSフィード
